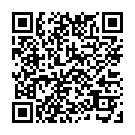分類
2024年04月08日(月)
新任式・始業式
4月8日(月),新任式では校長先生をはじめ10名の先生方をお迎えし,ごあいさつをいただきました。
始業式では,校長先生が本校のスローガンとして掲げた「元気な挨拶と,ありがとうがたくさん飛び交う,明るく,楽しい学校」に込める思いなどをお話になりました。
つづいて,生徒指導主任・進路指導主任・保健主任から令和6年度がスタートするにあたっての心構えについてお話がありました。
生徒の皆さんは先生方のお話に真剣に聞き入っていました。2024年04月01日(月)
シャクナゲが満開!
春の陽気がやって来ました。
「もうそろそろ咲きますよ。」と話されて転出された先生方のお言葉どおり,新年度のスタートを祝うかのようにシャクナゲが咲きました。

2024年03月26日(火)
表彰式・終業式・離任式
3月25日(月),表彰式・終業式・離任式をおこないました。
表彰式では,1カ年皆勤5名,日本漢字能力検定2級1名,実用英語技能検定準2級2名と全国高等学校家庭クラブ功労賞の表彰を行いました。
終業式では,校長先生より令和5年度の振り返りと令和6年度に向けての心構えについて御助言をいただきました。
離任式では本校を転出される先生方から,在校生へ向けてお言葉を賜りました。転退職される先生方鹿児島東高校のためにご尽力いただきありがとうございました。
先生方の今後のご活躍とご多幸をお祈りいたします。
2024年03月22日(金)
森川校長先生による特別講義
3月18日(月)の6時間目に,3月で役職定年を迎えられる森川校長先生による特別講義がありました。
校長先生はこれまでの経験を紹介しながら,未来を担う生徒及び職員の皆さんに向けたメッセージを講話に込めてくださいました。
そして,生徒会長の木場君は,「森川校長先生の半生を知ることができ,校長先生の存在をとても身近に感じた瞬間でした。もう少し早く聞きたかったと思いました。」と締めくくりました。
森川校長先生!おつかれさまでした。そして,ありがとうございました。
2024年03月14日(木)
合格者集合
本日,午前中に合格者及び保護者等にお集まりいただき,説明会を行いました。
学校からは,スクールミッションや入学式までの過ごし方,諸手続きのことなどについて説明を行いました。
説明会のあとは入学前面談や教科書販売等が行われ,4月から始まる高校生活への期待が高まっていました。
入学式までにしっかり準備をしておいてください。
皆さんのご入学を心からお待ちしています。

2024年03月04日(月)
令和5年度卒業式
令和6年3月1日(金),令和5年度(普通科第53回)卒業式が挙行され,卒業生34人が希望に満ちた大空へ羽ばたいていきました。卒業生の皆さん,保護者及び関係者の皆様,御卒業おめでとうございます。
2024年01月01日(月)
謹賀新年
新年,明けましておめでとうございます。
令和6(2024)年も鹿児島県立鹿児島東高等学校をよろしくお願い申し上げます。

2023年12月22日(金)
2学期終業式・表彰式
12月21日(木)午前中に終業式・表彰式を実施しました。
終業式に先立ち表彰式を行い,日本漢字能力検定2級合格者2名,実用英語技能検定合格者1名,第74回鹿児島県高校美術展優秀賞1名,秀作賞1名,奨励賞3名が登壇し,合格証及び賞状が授与されました。おめでとうございます。
また,終業式では校長先生が2学期の講話のエッセンスを集約して話され,加えて新年を迎える私たちに「自らの道は自ら切りひらく」,「できない理由を考える前に,できる方法を考える」,「成功するまであきらめない」という3つの言葉を与えてくださいました。お手元のタブレットでパワーポイントを操作しながら語りかける分かりやすい講話は,みなさんの心に届くお話で,生徒たちも聞き入っていました。

2023年12月15日(金)
出前授業を開催しました!
12月15日(金)の5,6時間目を活用して,1・2年生を対象に進路意識の向上及び進路選択の一助とするために,外部講師を招いて出前授業を開催しました。
講師の皆様の専門性を打ち出したわかりやすい授業に生徒たちは集中して取り組んでいました。
関係者の皆様,ありがとうございました。
2023年11月29日(水)
「アジアん☆鹿児島」で大活躍!
11月25・26日(土・日)に鹿児島市(宝山ホール・鹿児島市中央公園)で開催された「アジアん☆鹿児島」に本校生がボランティアとして参加しました。
生徒たちは事前の広報活動に参加したり,壇上に上がりゲームに参加してコメント役を務めるなど大活躍しました。